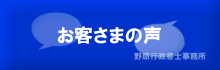- 単純承認=プラス財産もマイナス財産も全て相続すること。
- 相続放棄=マイナス財産が多い時に、全てを放棄すること。単独で出来る。
- 限定承認=プラス財産の限度まで借金を払うこと。相続人全員の合意が必要で、単独ではできない。
津市で開業している野原行政書士事務所です。遺産相続関連のご相談を専門に承っております。相続手続きや遺言書作成等相続全般に関し、専門に業務を行っています。
親身になり丁寧かつ迅速をモットーに取り組んでおりますので、お気軽にご連絡ください。
津市で開業している、野原行政書士事務所です。遺産相続関連のご相談を専門に承っております。例えば葬儀後の手続き、相続人の範囲、遺産総額、財産分割、遺留分、遺言書作成、そして終活対策などがあります。円満な相続になることを喜びとし、親身になり丁寧かつ迅速をモットーに取り組んでおりますので、お気軽にご連絡ください。
相続の手続について
相続の手続きは役所や銀行、保険会社等との関係で、書類が多く、初めての方は大変です。チェック表をつくり優先順番を決め、急ぐものから順番に進めましょう。
1 死後すぐしなければならない手続き
-
死亡届の提出
期限:7日以内に
提出先:住民票のある役場へ
必要書類:死亡診断書または死体検案書
(死亡診断書は病死で医師が発行、死体検案書は事故死、突然死で警察の監察医などが発行) -
年金受給停止届の提出
期限:10日以内に
提出先:厚生年金は年金事務所または国民年金は市町村役場へ
必要書類:死亡届、年金証書、死亡診断書又は確認できる戸籍謄本
※関連ニュース:年金不正受給事件 「東京都足立区の男性が7年前に死亡したのに、遺族は年金受給停止届を怠り、1200万円の年金を不正に受給していた。厚労省は返還請求をし、また警視庁に詐欺罪で告訴も視野に入れている。2013年8月」 -
介護保険資格喪失届の提出
期限:14日以内
提出先:市町村役場
必要書類:特になし
- 世帯主変更届(14日以内に住民票のある役場へ)
- 各種公共料金の名義変更
2 葬儀終了後すみやかに手続きが必要な手続き(世帯主が亡くなった場合)
-
遺族厚生年金(国民遺族基礎年金)の請求
請求先:年金事務所または市町村役場
必要書類:年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書、源泉徴収票、住民票、振込先口座名ほか必要書類は事前に確認
-
その他 健康保険の切り替え
※お得情報:葬祭費・埋葬料がもらえます。
申請により数万円程度支給されます。申請を忘れないように。
申請先:健康保険は「埋葬費」で健康保険組合へ、国民健康保険は「葬祭料」として市町村役場へ請求して下さい。(請求期限は2年以内)
3 返却が必要なもの
- 運転免許証
- パスポート
-
クレジットカード(年会費が自動引き落としになることが多い)
※お役立ち:最近の役所は住民サービスがかなり浸透し、市町村役場や法務局等分からないことがあれば、まず窓口や相談コーナーを利用してみることもお勧めです。以前よりはかなり親切になってきてます。
諸手続きが終えましたら、いよいよ相続に入ります。一般的に四十九日の法要を終えるころから相続の話が出てきます。
4 相続手続きの流れ
 相続の開始
相続の開始 1 葬儀

2 初七日法要

3 四十九日忌法要
 遺言書の確認
遺言書の確認 1 遺言書があれば家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。
※もう少し詳しく:検認とは遺言書が間違いなく本人のものであることを確認し、証拠として保管しておくためのもの。これを怠ると5万円の罰金と法律で決まっています。但し、公正証書遺言は検認の必要はありません。

2 遺言書があれば原則遺言書の指示通りの財産分割になります。

3 遺言書がなければ相続人間の協議となります。
 相続人と相続財産
相続人と相続財産 1 相続人の確定

2 相続財産・債務を調査

3 財産目録の作成

4 調査の結果をもとに、相続の受け方には3通りありますので、慎重に選択してください。

- 相続放棄は相続を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てが必要です。悪質な業者は3か月間は沈黙し、3か月過ぎてから催促してくることがあります。3か月というのは、亡くなってからではなく相続があることを知ってからですのでお間違いなく。たとえ3カ月経過していても助かる場合がありますので、ご相談下さい。
- 放棄しますと、相続権は次の順位の相続人に移行し、思わぬ借金の請求を受けることになりますので注意して下さい。
 財産分割
財産分割 1 財産分割について相続人間で話し合い

2 成立すれば「財産分割協議書

3 作成

4 成立しなければ家庭裁判所へ調停

5 申請
 名義変更と相続税の計算
名義変更と相続税の計算 1 遺産分割協議書に基づき名義変更

2 相続税計算
相続税の発生なければ税務署への申告は必要ありません。
相続税の支払いが必要であれば相続発生後10か月以内に納付しなければなりません。
相続税の支払いが必要であれば相続発生後10か月以内に納付しなければなりません。
 相続税の納付は相続発生より10か月以内厳守!!、無断で超過すれば税軽減になる基礎控除が適用されなくなり大変です。期限内が難しければ、税務署に延長の申請をすれば、許可されるようになってます。
相続税の納付は相続発生より10か月以内厳守!!、無断で超過すれば税軽減になる基礎控除が適用されなくなり大変です。期限内が難しければ、税務署に延長の申請をすれば、許可されるようになってます。